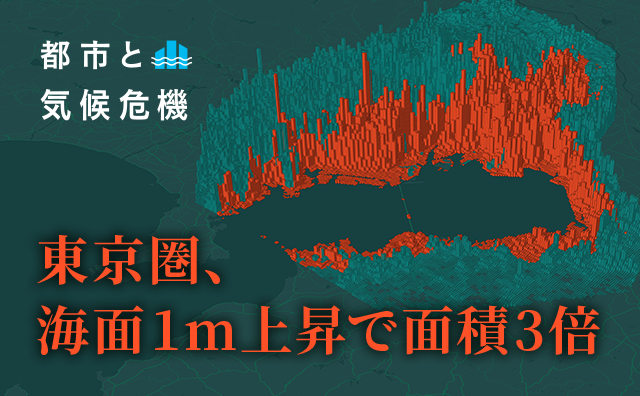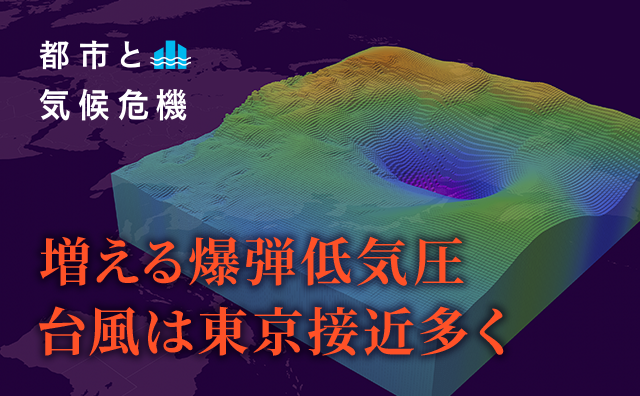ヒートアイランド
高まる熱中症リスク
東京・大阪・名古屋 搬送データ分析
地球温暖化とともに、地表面の被覆や人工排熱の増加によって郊外よりも気温が高くなる「ヒートアイランド現象」が都市を温め続けている。気温上昇に伴い、日本の主要都市では熱中症のリスクが高まっている。救急搬送者が発生する場所で最も多いのは住宅だが、今回は特に三大都市の屋外にも着目しながらリスク地域を調べた。
衛星画像で
各都市の
都市化を分析
日本経済新聞は、JAXA(宇宙航空研究開発機構)が公開する都市の人工衛星画像を基に全国の都道府県庁所在地と政令指定都市の計52都市を対象に半径10キロ圏のアスファルトやコンクリートなどによる舗装面積の比率である「都市化率」を分析した。山口市の9%、松江市の13%に対し、東京23区と大阪市は93%だった。
都市化の影響は1日の最低気温で顕著に表れるとされる。1941~50年と2011~20年の8月に記録した最低気温の平均の差をみると名古屋市は2.6度、大阪市は2.3度上昇したのに対し、松江市は1.2度の上昇にとどまる。都市化が進むほど、気温が上昇する傾向が見られた。
都市化率の見方
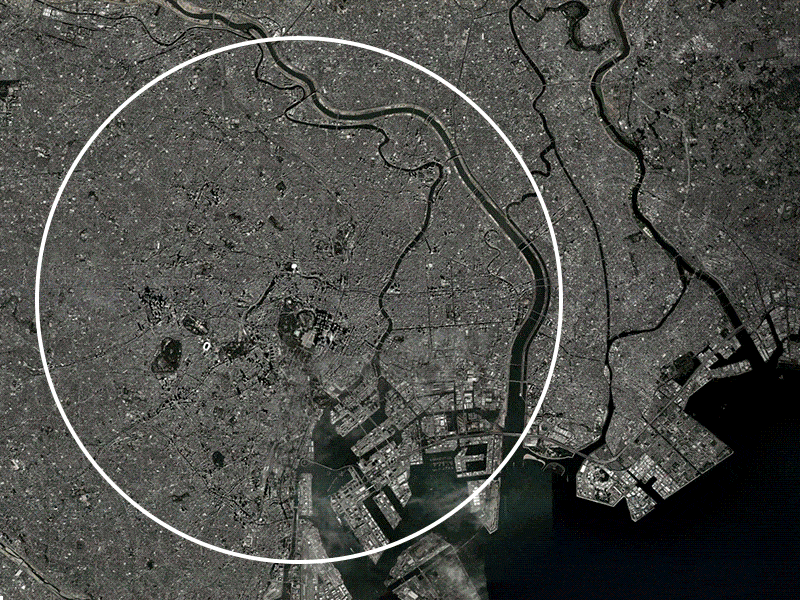
JAXAが公開している陸域観測技術衛星「だいち」のデータから作成した高解像度土地利用土地被覆図を利用して、主要52都市の中心部から半径10キロ圏の土地利用の比率を算出した。水域は除き、「人工物」「緑地」「公園・農作地」「その他」の4種類に分類した。
主要52都市の都市化率
土地被覆
札幌
-
人工物00.00%
-
緑地00.00%
-
公園・農作地00.00%
-
その他00.00%
*1941~50年と2011~20年の8月の月最低気温差
気温上昇に伴い
熱中症搬送者が増加
主要都市の熱中症搬送者数
注:各都市の消防当局、国立環境研究所のデータをを基に作成。各年の5~9月に発生した救急搬送者数を集計
日本経済新聞は、熱中症に詳しい国立環境研究所の小野雅司客員研究員の協力を得ながら、5~9月に主要52都市で発生した熱中症の搬送者数について2021年までの入手可能な期間のデータを調べた。救急搬送者数は10年から増加傾向で、記録的な猛暑だった18年には東京23区は5788人、大阪市は2191人、名古屋市は2079人とピークに達した。20年以降はコロナ禍に伴う外出自粛などで減少傾向だが、22年は猛暑が続く。温暖化の進行で「今後、搬送者数は猛暑だった18年のピークを数年ごとに超える可能性がある」(国立環境研の小野客員研究員)。
周辺区のリスク、
東京は6倍、大阪は8倍、名古屋は2倍
東京、大阪、名古屋を対象に比較可能な過去5年間(2017~21年)の5~9月の搬送者数のデータを詳しく分析した。熱中症は昼間に多発するため、昼間人口10万人(20年)あたりの平均搬送者数を東京23区と大阪市24区、名古屋市16区でみると、中心区は少なく、周辺区が多いドーナツ状の分布がみられた。東京は最多の足立区と最少の千代田区で6倍、大阪は西成区と中央区で8倍、名古屋でも港区と中区で2倍の開きがあった。
東京都立大学の藤部文昭特任教授は「東京の搬送者数は高温の内陸部と比較的涼しい臨海部で大きな差がない。大阪と名古屋では臨海部で多い傾向がみられる。自然要因だけでなく、生活環境などの社会的要因も大きく関わっているのではないか」と指摘する。
住宅に次ぎ、
道路での発生が多い
注:各都市の消防当局の2017~21年のデータを基に作成。仕事場や教育機関の発生場所は屋外と屋内の両方が含まれる
発生場所で最も多いのは住宅で約4割。エアコンを利用しないケースが多いとみられる。続いて多かったのは道路で2~3割を占めた。
発生場所と生活環境の関係を探るため、人口に占める高齢者の比率、推計年収など様々な指標と搬送者数を分析。国土交通省が公開する国土数値情報を基に各区の面積あたりの駅数を計算した「駅密度」に着目すると、駅密度が高い中心区は搬送者が少なく、低い周辺区は多いという公共交通機関の充実度との関係が浮かび上がった。
注:東京消防庁、国土交通省国土数値情報のデータを基に作成
© Mapbox © OpenStreetMap © Maxar
注:大阪市消防局、国土交通省国土数値情報のデータを基に作成
© Mapbox © OpenStreetMap © Maxar
注:名古屋市消防局、国土交通省国土数値情報のデータを基に作成
© Mapbox © OpenStreetMap © Maxar
東京
足立、葛飾、北区が多く
足立、葛飾、北、荒川、台東など北部や東部の9区で平均搬送者数が40人を超えた。平均搬送者数が多い区で昼間人口に占める高齢者の割合をみると、東京の足立、葛飾、北区などが約3割と他区に比べ高かった。
また、これらの9区の1平方キロあたりの駅の数は江戸川区(0.2駅)など5区が1駅未満で、千代田区の5.5駅、中央区の3.2駅との差は大きかった。
搬送者数が57.4人の足立区に住む60代の女性は「駅まで15分かけて歩くことも多い。気温が30度を超えるときつくなる」と話す。駅前や幹線道路沿いはスーパーやコンビニエンスストアで涼むこともできるが、「住宅地は高い建物がほとんどなく日陰も少ない。夏の昼間は日照りがきつい」(70代の男性)。
搬送者数が55.6人の葛飾区の担当者は「葛飾区は南北を移動するのにバスを利用する必要があり、歩いたり、バス停で待っていたりする時に体調を崩す人も多いのではないか」と話す。同区は約60の公共施設などのスペースを猛暑時の一時的な避難・休憩場所として9月末まで開放している。
| 区 | 10万人あたりの 熱中症搬送者数 | 交通の充実度 (駅密度) |
|---|---|---|
| 足立区 | 57.38 | 0.56 |
| 葛飾区 | 55.62 | 0.52 |
| 北区 | 48.61 | 1.21 |
| 荒川区 | 44.0 | 2.95 |
| 練馬区 | 42.34 | 0.56 |
| 台東区 | 42.26 | 2.77 |
| 板橋区 | 42.19 | 0.62 |
| 墨田区 | 41.56 | 1.45 |
| 江戸川区 | 41.21 | 0.22 |
| 豊島区 | 38.2 | 2.69 |
| 大田区 | 37.62 | 0.79 |
| 江東区 | 36.79 | 0.91 |
| 杉並区 | 36.18 | 0.68 |
| 中野区 | 32.78 | 1.03 |
| 世田谷区 | 32.01 | 0.76 |
| 目黒区 | 27.37 | 0.68 |
| 品川区 | 24.84 | 1.75 |
| 渋谷区 | 23.8 | 2.25 |
| 新宿区 | 21.55 | 2.69 |
| 文京区 | 19.12 | 1.77 |
| 港区 | 11.10 | 2.85 |
| 中央区 | 9.98 | 3.23 |
| 千代田区 | 9.32 | 5.49 |
大阪
西成区の搬送者、全国でもトップ
南西部に位置する西成区は平均搬送者数が127.8人と同市内だけでなく、全国でトップとなった。同区の高齢者の割合は約4割と他区に比べはるかに高い。大阪公立大学の生田英輔教授(防災工学)らの分析によると、区内で最も搬送者が多いのは日雇い労働者の街「あいりん地区」付近だ。同地区で職業紹介事業を手掛ける西成労働福祉センターの松井環総務課長は「この地区では路上や広場で交流する人が少なくない。涼しい環境が整えられていないことが熱中症搬送者が多い原因の一つではないか」とみている。同センターは冷房が効いた待合所を開放している。
西成区に続くのは此花区や鶴見区、住之江区など。キタやミナミといった中心部から離れた周辺区にあり、1平方キロあたりの駅の数は1駅に満たず、中央区(3.8駅)などと比べ交通の便は悪い。大阪市健康局の片桐幹雄健康施策課長は「市中心部では熱中症で搬送されるという印象はあまりない。周辺区は駅が少なく道を移動することが多いことが原因かもしれない」と話す。
| 区 | 10万人あたりの 熱中症搬送者数 | 交通の充実度 (駅密度) |
|---|---|---|
| 西成区 | 127.83 | 2.17 |
| 此花区 | 70.26 | 0.42 |
| 鶴見区 | 62.34 | 0.49 |
| 住之江区 | 61.98 | 0.68 |
| 港区 | 60.79 | 0.51 |
| 大正区 | 60.58 | 0.21 |
| 平野区 | 54.56 | 0.46 |
| 東住吉区 | 54.21 | 0.72 |
| 生野区 | 50.54 | 0.6 |
| 都島区 | 48.44 | 0.99 |
| 住吉区 | 48.11 | 1.17 |
| 東成区 | 47.91 | 1.32 |
| 阿倍野区 | 45.29 | 1.67 |
| 旭区 | 43.69 | 1.42 |
| 城東区 | 43.52 | 1.55 |
| 浪速区 | 41.3 | 3.42 |
| 天王寺区 | 40.02 | 3.1 |
| 西淀川区 | 38.78 | 0.35 |
| 淀川区 | 35.78 | 1.11 |
| 東淀川区 | 34.01 | 0.83 |
| 福島区 | 25.63 | 1.93 |
| 西区 | 21.75 | 2.3 |
| 北区 | 20.98 | 2.61 |
| 中央区 | 16.87 | 3.83 |
名古屋
中区除き搬送者数多く
昼間人口10万人あたりの平均搬送者数が港区は64.2人。最少となった中区の26.6人との差は2倍にとどまるものの、16区のうち13区が40人超と、東京や大阪と比べても中心区を除きほぼ全域で搬送者数が多い。昼間人口に占める高齢者の割合をみると中区は1割と、他区の2~3割に比べ低い。1平方キロあたりの駅の数も、中区は2.4駅だが港区を含む13区は1駅未満だ。
| 区 | 10万人あたりの 熱中症搬送者数 | 交通の充実度 (駅密度) |
|---|---|---|
| 港区 | 64.24 | 0.22 |
| 北区 | 58.25 | 0.63 |
| 南区 | 56.18 | 0.7 |
| 守山区 | 54.43 | 0.18 |
| 瑞穂区 | 52.78 | 0.89 |
| 中川区 | 49.24 | 0.34 |
| 中村区 | 49.11 | 1.29 |
| 千種区 | 48.25 | 0.72 |
| 熱田区 | 44.18 | 0.98 |
| 天白区 | 43.91 | 0.28 |
| 緑区 | 43.19 | 0.24 |
| 昭和区 | 42.47 | 0.73 |
| 東区 | 40.98 | 1.43 |
| 名東区 | 38.68 | 0.21 |
| 西区 | 38.61 | 0.61 |
| 中区 | 26.61 | 2.35 |
全国では鳥取、高知、佐賀が高リスク
高齢者比率、都市の集約度関係も
全国の県庁所在地と
政令指定都市の
熱中症救急搬送者数
昼間人口10万人あたりの
熱中症搬送者数
注:2017~21年5~9月平均、昼間人口は20年。各県庁所在地と政令指定都市の消防当局のデータを基に作成
*1はコロナ禍の影響で20年5月の搬送者数が不明
*2は受託市町村の搬送者数と昼間人口を含む
全国の都道府県庁所在地の昼間人口(2020年)10万人あたりの過去5年間(17~21年)平均の熱中症搬送者数を算出した。その結果、鳥取市と高知市がいずれも82.2人で最多となり、東京23区(31.1人)と比べリスクは2.6倍にあたる。佐賀市(80.2人)、熊本市(68.9人)、福島市(68.2人)が続く。60人を超えたのは10都市に上り、すべてが地方都市だ。一方、川崎市(29.9人)、横浜市(32.9人)、福岡市(34.8人)など人口100万人超の大都市では発生率が低かった。
全国の県庁所在地と
政令指定都市の
「暑さ指数」
- 注意:一般に危険性は少ないが激しい運動や重労働時には発生する危険性がある
- 警戒:運動や激しい作業をする際は定期的に充分に休息を取り入れる
- 厳重警戒:外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する
- 危険:高齢者においては安静状態でも発生する危険性が大きい
国立環境研究所、気象業務支援センターのデータを基に作成
2017~21年の5~9月の「暑さ指数」の最高値で「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」に達した日数の割合を示す。川崎は横浜、相模原は八王子の数値を採用
昼間人口10万人あたりの熱中症搬送者数が多い順に掲載
リスクが高い都市は西日本が目立つが、詳しく分析すると、いくつかの要因が考えられる。まず環境省が気温や湿度などを基に算出する「暑さ指数」。過去5年間の5~9月の期間中、熱中症患者が著しく増加するとされる「厳重警戒」以上だった日が占める割合は全都市平均で35.2%だが、高知市43.8%、熊本市46.4%など、同指数の高さが搬送者数の多さに表れた。
また高齢者は熱中症に弱いとされるが、昼間人口10万人あたりに占める高齢者比率を見ると、鳥取市、高知市、佐賀市は28~31%と全都市平均の24%を上回った。
さらに市の全人口のうち人口集中地区に住む市民の割合である「都市の集約度」は、自宅から病院や商業施設への距離など都市生活の利便性の高低を表すが、佐賀市は全都市で最も低かった。集約度の低い20都市のうち、14都市が搬送者数50人以上となった。
ただ、熱中症リスクが46位の東京23区、同42位の福岡市でも約4割の日数で暑さ指数が厳重警戒以上となったほか、同51位の静岡市の高齢者比率は高知市を上回る30%となるなど、熱中症の発生要因は一概でなく、複合的で地域によって異なる。
近未来には
大都市でも
搬送者が増加
筑波大学が予測した
熱中症搬送者数の増加率
注:筑波大学日下研究室のデータを基に作成
© Mapbox © OpenStreetMap © Maxar
筑波大学の日下博幸教授(気象学)らの研究グループは、現状(1981~2000年)から近未来(2031~50年)にかけての1都3県の救急搬送者数の増加率を予測した。温暖化対策を実施しないシナリオでは、東京都港区と中央区、千代田区が4.4倍、川崎市高津区が4.3倍、横浜市都筑区が4.2倍、千葉市緑区が4倍など、人口が多い大都市で大幅に増える見通しとした。「温暖化の効果に加え、高齢者の数が増えるからだと考えられる」(日下教授)
世界で進む
暑さ対策
2022年は海外でも記録的な熱波が各地を襲っている。英国は7月、ロンドン郊外で観測史上最高の40度超を記録、フランスも連日40度超を観測した。暑さへの対策が進んでいる。
ワシントン
提供:米大気海洋局 注:気温マップのイメージ
米国の首都ワシントンでは、猛暑にさらされたときに影響を受けやすい地域を特定して、街づくりや植樹、住民への注意喚起に生かしている。
ワシントンのエネルギー環境局や運輸局は、バージニア科学博物館のジェレミー・ホフマン主任科学者や市民ボランティアらが作成した地域の詳細な気温分布地図に年齢や収入などの人口統計データを重ね合わせた。暑さに弱い住民が多い地域をあぶり出し、街づくりや植樹といった事業の優先順位の決定に生かしている。ホフマン氏は「多くの都市では気温ではなく地表面の温度データを使っているが、対策を練るのに十分な詳細さではない」と指摘する。地表面の温度と、実際に人が生活する地上数メートルの気温は必ずしも一致しないためだ。ホフマン氏は「細かい気温分布図で、住民の安全を守るために的を絞った対策が可能になる」という。
メルボルン
オーストラリアで人口約508万人と2番目に多いメルボルン市。気温が40度を超える日が毎年続いている。そこで市が乗り出したのが、日陰や避暑地帯が多い道を優先的に案内するルート検索サービス「Cool Routes」だ。ロイヤルメルボルン工科大学発の地図情報活用スタートアップのスペイシャル・ビジョンと連携し、航空写真などを基に緑地が多い地域を特定。さらに建物の影や日射による道路の蓄熱なども考慮に入れたデータセットを用意し、ルート検索サービスを連携させた。暑熱から逃れられる道順を案内できるようにした。
- 一般的な案内ルート
- Cool Routes
注:サービスのスクリーンショットに加筆
現在は市中心部やメルボルン大学がある市内北部など3エリアのみが対象だが、同市によると「市内全体をカバーできるように拡張していく予定」という。
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は、2月に公表した第6次評価報告書で「気候変動とそれに伴う極端現象は、短期から長期にわたって、健康障害及び早期の死亡を大幅に増加させる」と警告している。世界保健機関(WHO)も気候変動に伴う高温による健康被害などの死者が2030〜50年には、年間で約25万人増加すると予測している。人々の健康や命を守るための行動が求められる。
調査・分析の方法
都市化率の分析では、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が公開する高解像度土地利用土地被覆図のデータを基に各都市中心部から半径10キロメートルの範囲の土地利用状況を調べた。熱中症の救急搬送者数の発生率は、各都市を管轄する消防当局から提供を受けた搬送者数データと国勢調査(2020年)による昼間人口を用いて算出した。駅密度は、鉄道事業法で運営する鉄道駅の数を各区の面積で割って求めた。ただし大阪メトロの軌道法で運営する路線は利用者数が多いため計算に加えた。
都市と気候危機シリーズ